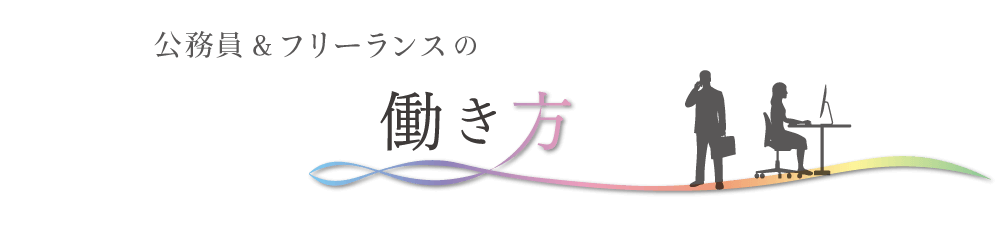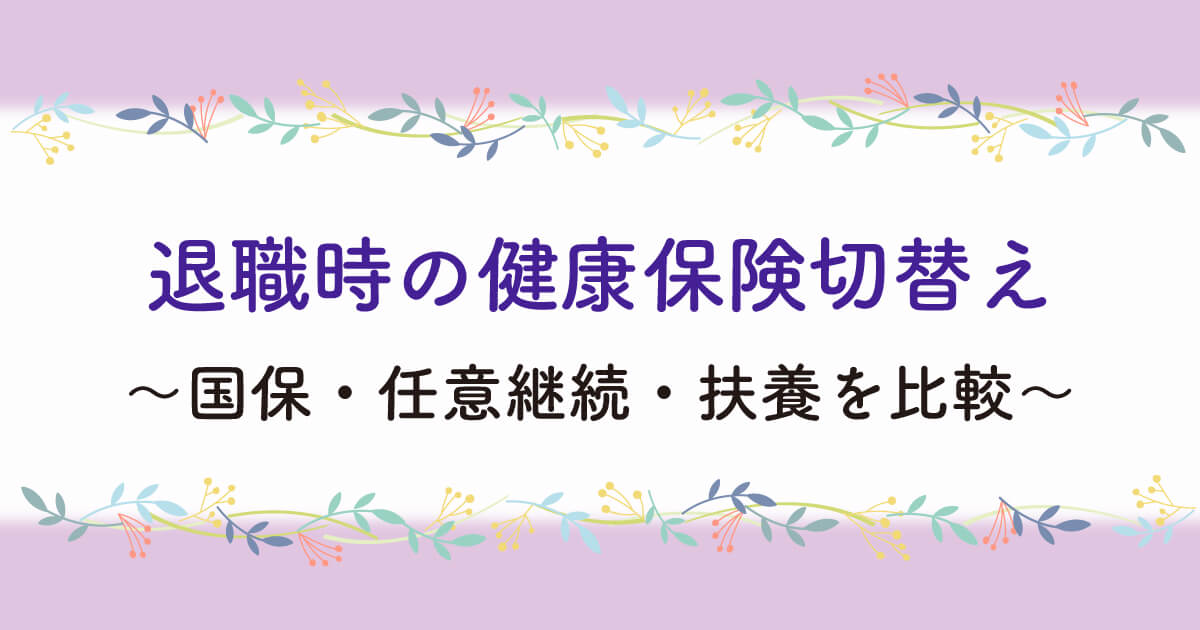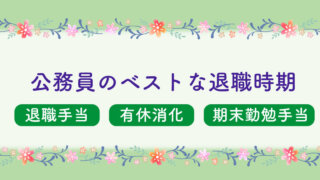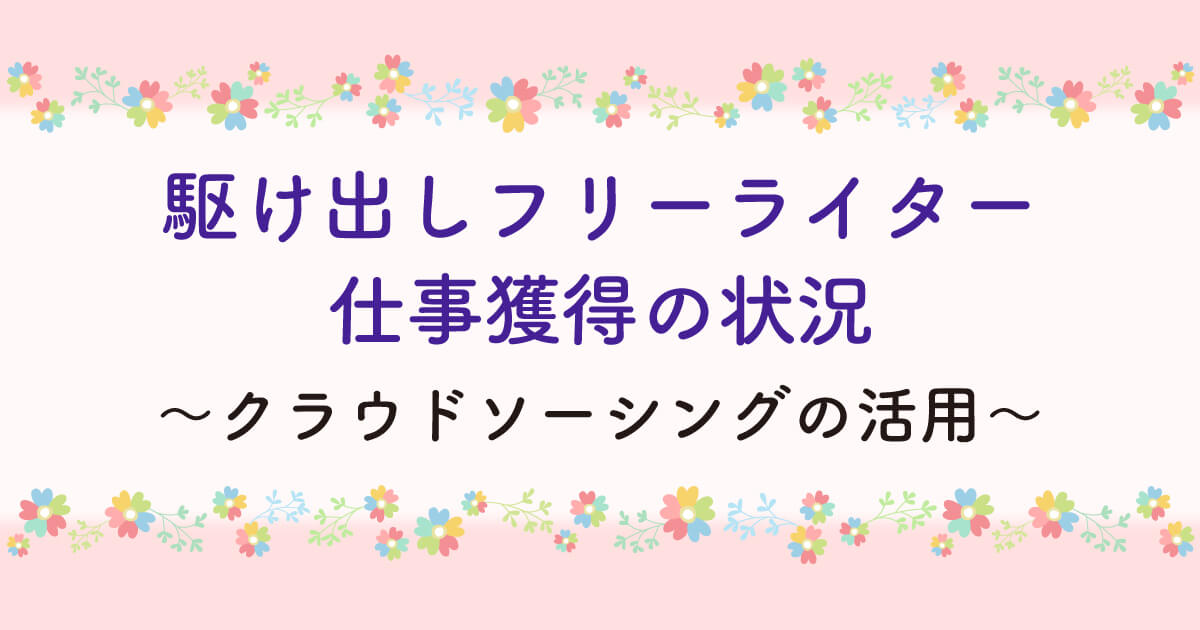こんにちは!元公務員フリーランスのレイです。
当サイトをご覧いただきありがとうございます。
退職時の健康保険の切替えについてお悩みですか?
企業・団体間で転職する場合は転職先が加入する健康保険組合に移行すればいいですが、
しばらく働かない場合や独立する場合などは選択肢が複数あるので悩みますよね。
この記事では、私自身の退職時に調べたことや実際に行った手続きについてご紹介します。
退職時の健康保険の切替えについてお悩みの方、ぜひ参考にご覧ください。
退職時の健康保険切替え:選択肢は3つ
退職後すぐに企業や団体に転職しない場合、健康保険を退職前の職場の組合から切り替える選択肢は以下の3つです。
- 国民健康保険に加入する
- 退職前の健康保険を任意継続する
- 家族の扶養に入る
詳しく解説しているサイトは他に多数あるので、ここでは要点を絞って触れていきますね。
国民健康保険に加入する
国民健康保険(国保)とは、病気やケガをした場合に安心して医療を受けることができるよう、加入者が普段から保険料(税)を納め医療費の負担を支えあう、助け合いの制度です。
国保は、すべての人が何らかの医療保険に加入することとなっている我が国の「国民皆保険制度」の中核として、地域住民の医療の確保と健康の保持増進に大きく貢献しています。
(公益社団法人国民健康保険中央会HPより引用)
日本では、国民は全員が何らかの医療保険(健康保険)に加入しなければなりません。
このため、退職に当たり後述する「任意継続」または「家族の扶養に入る」のいずれかの手続きをしない場合は、消去法で国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の特徴で大きいのは、保険料が自治体ごとに異なる点です。
自分が支払う保険料額がいくらになるかを知るには、区市町村のHPを見るなどして自分で計算する必要があります。
まずは国民健康保険の金額を計算してみてから、後述の任意継続と比較すると良いでしょう。
退職前の健康保険を任意継続する
任意継続被保険者制度は、「健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度」です。
(厚生労働省社会保障審議会医療保険部会(平成28年9月29日)資料より引用)
・保険料:全額被保険者負担(事業主負担なし)
任継継続の大きな特徴は、退職後(被保険者の資格喪失後)20日以内に手続きしなければならないこと。
つまり、国民健康保険や家族の扶養に一旦入ると、もう任意継続保険に入れないのです。
これに対して、国民健康保険はいつでも加入できます。
また、このほかの違いとして、家族が自分の扶養に入っている場合の取扱いがあります。
任意継続した場合は退職前と同様に追加負担なしで扶養扱いにできますが、国民健康保険では家族一人一人が国民健康保険に加入することになりますので、留意が必要です。
家族が加入している健康保険の扶養に入る
扶養に入るための手続きなど細目については各健康保険組合によって異なりますが、
「被扶養者の範囲」は法律(健康保険法第3条第7項)に定められています。
被扶養者の収入の上限は、59歳以下(障害年金を除く)の場合は月額108,334円未満(年収換算で130万円未満)となります。※2019年12月現在
収入要件は、将来に向かっての見込み年収で判断されます。
年の途中の退職で既に年収が130万円以上になっていても、関係ないんだね。
私がいったん任意継続した経緯・理由
ここからは、私の場合はどうだったかを紹介します。
当初、「扶養に入る」という考えがなかったので、国民健康保険と任意継続の二択で検討しました。
なんで扶養を考えなかったの?
すぐに収入上限を超えて扶養対象外になるなら、わざわざ手続きするメリットが少ないと思ったんだよね。
(最終的には扶養に移行しました。後で説明します!)
国民健康保険と任意継続。
どちらの方が保険料が安いか、自分で計算して比較しました。
結果、1年目(退職翌年の3月まで)は任意継続の方が年間で数万円安く、2年目(退職翌年の4月~翌3月)は国民健康保険の方が安くなるパターンでした。
このため、退職翌年の4月に国民健康保険に切り替えるつもりで、とりあえず任意継続の手続きをしました。
先述のとおり、国民健康保険はいつでも加入できるのに対し、任意継続は加入できる時期が限られています。
保険料がどちらも同じくらいであれば、とりあえず任意継続し、2年後又は途中で国民健康保険に切り替える方向で考えることをお勧めします。
扶養に入れる要件は健康保険組合ごとに違う!任意継続→扶養に移行しました
でも、任意継続の手続きをしたのに、その後結局扶養に入ったんだよね。
扶養の収入要件を判断する手続きが、健康保険組合によって異なるって知らなかったんだよー(汗)
先程、国民健康保険の被扶養者の収入上限についてご説明しました。
この収入上限を超えていないかの判定は、いつ・どのように行われるのでしょうか?
インターネットでいろいろなページを調べると、「直近3か月の収入額の平均で判断」と出て来るかと思います。
私は、これが自分にも当てはまると思い込んで、「月11万円弱の上限はすぐに超えるだろうから、わざわざ扶養に入らなくていいや」と判断してしまいました…。
ですが、後になって、フリーランス(個人事業主)の場合にいつ・どのように判定するかは、健康保険組合によって大きく異なることを知ったんです。
この点、厚生労働省にも電話で問い合わせてみたところ、
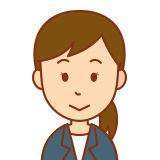
個人事業主の場合は、月ごとの収入を判断できる材料が乏しいので、確定申告時点で年1回判定している組合が多いようです。
ただ、開業後最初の確定申告前でも扶養に入れるかどうかは、健康保険組合によって取扱いが異なります。
ご主人が加入している組合に確認してください。
とのことでした。
こういう経緯で、急いで夫の健康保険組合の取扱いを確認した結果、
開業したてでも無事に扶養に入ることができました!
開業初年である2019年中は扶養の範囲内で仕事をしていたので、
私が夫の扶養からはずれるのは、最短で2021年3月の確定申告後となります。
保険料数十万円が節約できる!
これまで激務部署で頑張って沢山社会保険料支払ってきたし、一時的に甘えてもいいよね…?
今後、育児休業給付金などもらえないお金もあるしね。来年以降、扶養を脱せられるよう頑張って!
まとめ:扶養の取扱いについて家族の健康保険組合に確認しよう
いかがでしたでしょうか?
退職時はいろいろと手続きしなければならないことが多く、大変ですよね。
ただ、社会保険料は年額で数十万円にもなる大きなコストなので、後回しにせずしっかり検討することが賢明です。
健康保険の扶養に入ると、手続きをすれば国民年金も第3号被保険者になれますよ。
扶養に入れるかどうかは健康保険組合によって異なる部分もあるので、まずは家族が加入する組合に確認することをお勧めします!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!